



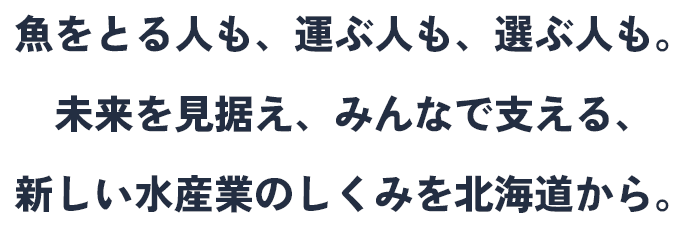
「コンソーシアム」とは、
共通の目標に向かって、
企業や行政、研究機関、
地域の人々などが
協力する仕組みのことです。
この水産業のコンソーシアムでは、
水産業者や流通業者、行政、大学、
そして消費者も含めた
多くの関係者が集まり、
持続可能な水産業のあり方を一緒に考え、
実践しています。
たとえば、「魚をとりすぎない方法」や
「効率よく届ける仕組み」
「公正な決済の仕方」など、
さまざまな課題に対して
デジタル技術や人材、
知恵を持ち寄って解決に向けた
方策を見出すとともに、
政策提言など発信を行うことで、
新しい水産業のモデルをつくる
新たな地方創生の取り組みです。
こうした取り組みを通じて、
水産業のエッセンスである
「魚」と携わる「人」を確保し
水産業の新しい未来をつくっていきます。
私たちが掲げたのが、4つの取り組み


資源を守るための制度や漁獲管理の仕組みが広がりつつありますが、「制度がわかりづらい」「急な変化に対応しにくい」といった不安や、現場の負担感も少なくありません。
栽培漁業や増養殖は、水産資源の安定供給に欠かせませんが、放流効果への疑問やコストの負担、遺伝的多様性への懸念、地理的制約など、課題も指摘されています。
地球温暖化や生態系保全の観点から、ブルーカーボンや藻場の役割が注目されていますが、地域での理解や日常的な維持管理の担い手が不足している現状もあります。
資源利用は、行政や漁業者だけで考える問題ではなく、流通・加工、実需者や消費者がそれぞれ問題意識を共有することが必要であり、講演会やシンポジウム等を通じ「サステナブル意識」の醸成を図ります。
科学的な評価や最新技術の活用を通じて、より効率的で環境にも配慮した方法を探っていきます。経済性と持続性を両立させ、現場にとって「取り組んでよかった」と思えるような形を目指します。
漁場機能の回復や魚の資源づくりにもつながる藻場造成、CO₂吸収源としてのブルーカーボンの取り組みを、未来の地域づくりの一環として位置づけます。ESGの考え方を活かしつつ、漁業者にとって経済的にメリットのある形で、持続的に取り組んでいきます。

水産業の未来を担う人がいない、過酷な現場、人口減少、構造の限界。北海道の水産業の現場は高齢化と人手不足に加え、急激な人口減少によって人材確保がますます困難になっています。
漁船の労働環境は過酷で、夜間操業や船内生活の厳しさから若者の定着が難しく、漁家子弟の離脱や世代継承の断絶も進んでいます。定置網漁などは市場ニーズに合わせた真夜中の操業が常態化し、働き方の見直しが必要です。
また、市場・加工・流通まで含めたすべての現場で人手不足が深刻化し、特に半島部・離島では外国人材の活用が欠かせ無い状態となっています。一方で、スマート化やデジタル化に必要な技術開発は、水産業の市場規模が小さいことから進みにくく、支援人材も不足しています。
地元だけでなく、地域外企業や関心ある人材を巻き込んだ将来像の再構築が必要であり、行政が近い将来を見据えた支援体制を強化することが求められています。
人口減少時代の“持続可能な働き方”を、技術と制度でつくる。
私たちは、行政や自治体と連携しながら、スマート機器やICTを活用した水産業DXの実装を進めています。
漁獲の見える化、自動化、省力化を通じて作業負担を軽減し、働きやすく魅力ある職場環境づくりを推進。あわせて、水産業ガイダンスや就業支援フェア、育成就労制度、外国人材との共存可能な現場設計も視野に入れています。
将来的には、地元の経営体・地域外企業・専門家・学界が連携して、沿岸・沖合の水産業、養殖、水産加工までを含めた産地の新しい担い手像・経営モデルの構築に取り組む必要があります。
こうした動きには、行政が主体となって制度・育成・設備整備を一体で支援する仕組みが不可欠です。
今後は、操業体制や就労環境の見直し、災害に備えた港湾整備、海洋環境の変化に対応する支援制度の強化を含め、「人が育ち、人が戻る、持続可能な水産業のあり方」をテクノロジーと共に形にしていきます。

日時も規格もバラバラな状態での出荷・輸送・販売の流れが、現場の負担になっています。規格や書類の統一が進まない中で、物流2024年問題も加わり、水産物流は制度と実態がかみ合っていない状況です。
水産業者・運送会社・卸売市場などの調整には、行政が橋渡し役として入ることの重要性が高まっています。物流インフラの整備・制度面の調整は、行政の主体的な取り組みが不可欠です。
私たちは、行政との連携により規格統一やデジタル化を推進し、共同配送やモーダルシフトの導入を実現します。また、産地市場再編や、生産から消費までの履歴を追跡できる「トレーサビリティ」の体制構築も、行政主導の支援策と連動して進めています。
地域・産地・流通を超えて行政と現場が連携する次世代サプライチェーンの実装を目指しています。

支払いが遅い、事務が多い、お金の流れが止まっている…
決済手続きが複雑で時間がかかる現状は、水産業の資金繰りに大きな影響を与えています。
とくに、小規模事業者は事務負担が大きく、資金の流れが滞りやすい構造です。法制度の壁もあり、行政と金融機関の制度設計が連携されていないことが障害となっています。
私たちは、行政が進めるペーパーレス・キャッシュレス推進の流れに対応した決済基盤の構築を目指しています。
取引様式の統一や支払いの迅速化を通じて、行政・金融と連携した水産業向けのスマート決済モデルを提案。法制度や補助制度との整合も重視し、行政のバックアップのもとで業界全体の信用向上と資金循環の最適化を図ります。